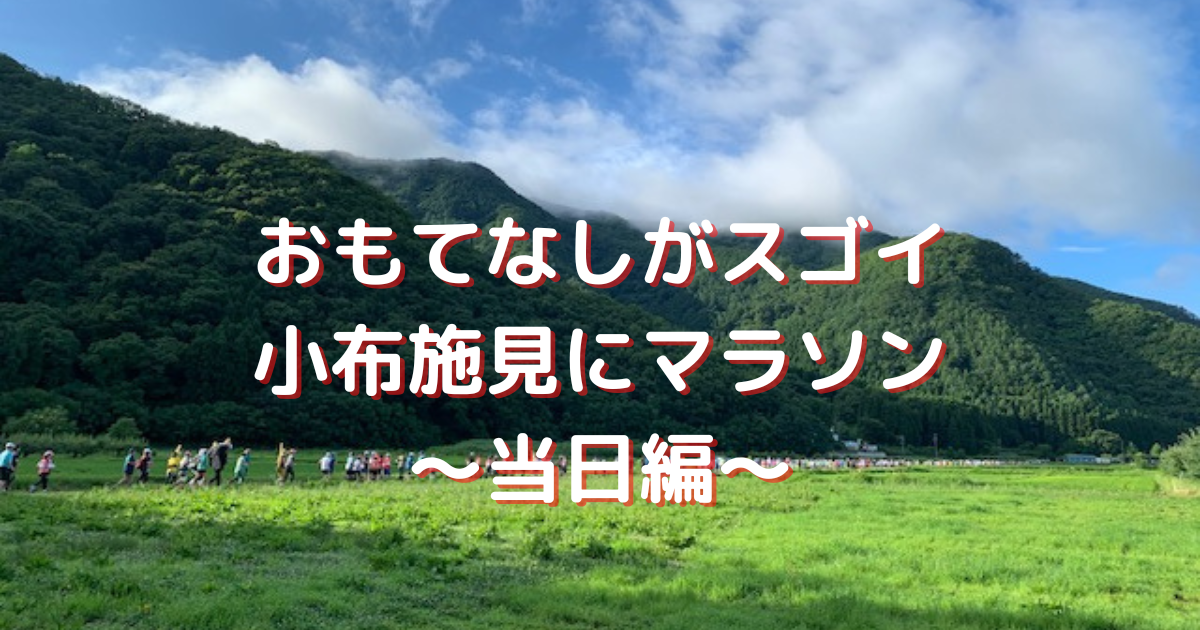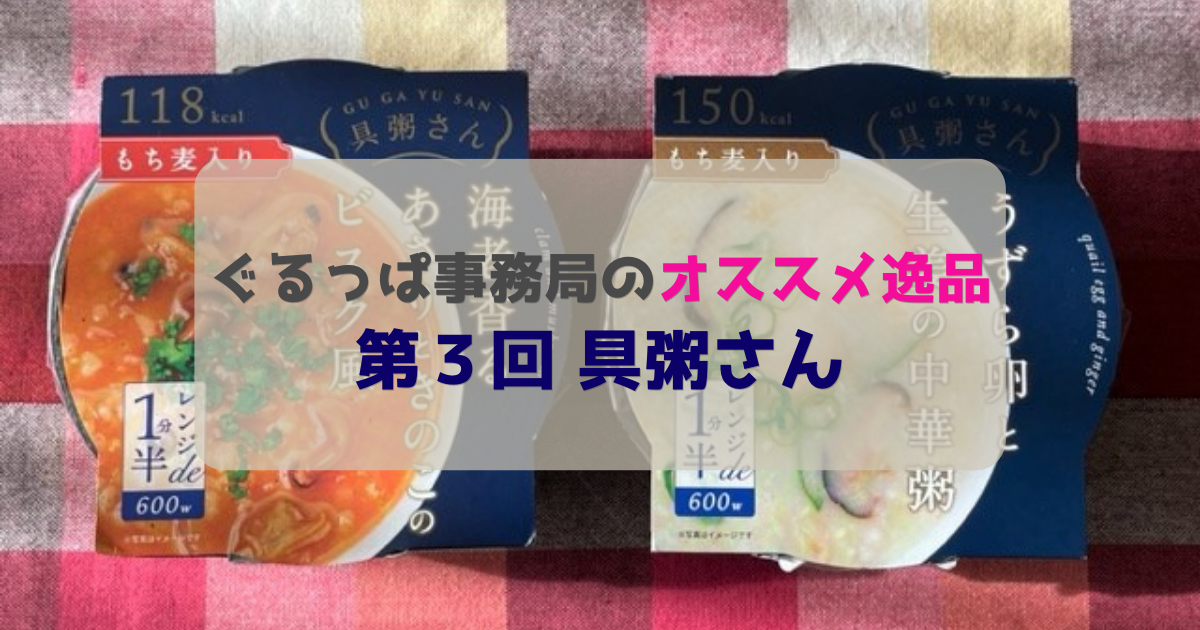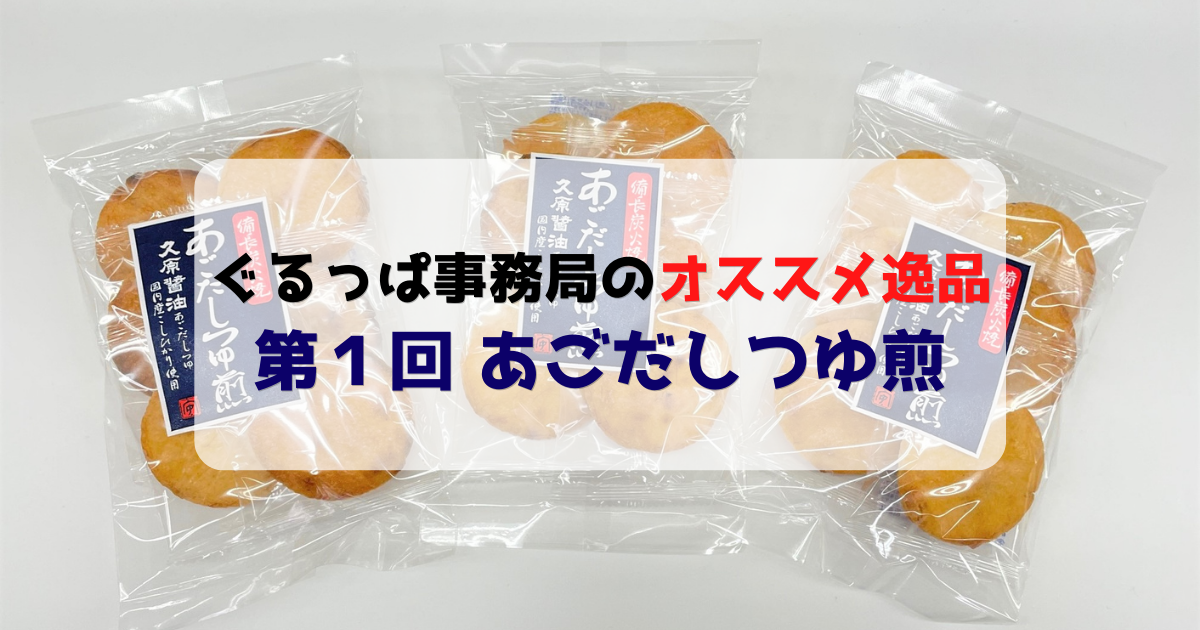

アンケート事例「春彼岸」2025
「ぐるっぱ」では、年間催事や旬の食・酒についてのアンケートを取っており、結果の一部を記事にして公開しております。今回は「春彼岸」についてのアンケート結果をご紹介いたします。なお、当記事は参照元アンケートの総回答者の中から、有効回答者のみを抽出して集計した結果について記載しております。それではご覧下さい。
「お彼岸は年2回」「春彼岸は春分の日前後3日」と知っている人の割合

上のグラフは、有効回答者(1618人)のうち「お彼岸は年2回」「春彼岸は春分の日前後3日」だと知っている人の割合を年代別に示したものです。
全体は65.9%ですが、20代は28.6%、30~40代は40%台、50代は64.9%、60代以上は8割弱となっていました。
20~40代のお彼岸の認知はかなり低くなっていますが、自らが一族の墓を管理する立場になれば、変わるのかもしれません。
墓参りに行くか?

「お彼岸は年2回」「春彼岸は春分の日前後3日」と知っている人(1067人)を対象に、お彼岸に墓参りに行くかを質問。
「行く」と回答した人は、全体では46.9%という結果になりました。
予想はしていましたが、若い年代ほど墓参りに行く人の割合は低くなっています。
70歳以上が最も墓参りに行くという人の割合が多いですが、それでも56.9%に留まっています。
お彼岸にお供えする物(食べる物)は?(複数回答可)

「おはぎ」「ぼたもち」という回答が4割弱を占めており、3番手以降の選択肢を大きく引き離しています。
3番手には、お供え物の定番である「果物」(17.0%)、4番手には「団子」(11.5%)が続きます。
5番手以降は極端に数値が低くなっていますので、これらをお供え物として用意しておけば大丈夫かと思います。
お供え物の購入先は?(複数回答可)

最多回答は「スーパー」で85.3%と圧倒的です。
多くの方が「おはぎ」「ぼたもち」「果物」「団子」と回答しているため、デイリー商品の取り扱いが豊富なスーパーが最多回答するのは当然でしたね。
「ぼたもち」と「おはぎ」の違いは何?(複数回答可)

最多回答は「基本的に同じもので呼び方が違うだけ」で選択率は42.0%でした。
2番手は「春がぼたもちで、秋がおはぎ」で選択率は37.8%でした。
3番手は「地域によって呼び方が違う」で選択率は24.2%でした。
上記回答はどれも正解ですね。
「ぼたもち」は漢字で書くと「牡丹餅」であり、「牡丹」は4~5月に開花する春の花。
一方、「おはぎ」は「お萩」であり、「萩」は8月中旬~9月中旬に見頃を迎える秋の七草。
基本的には同じものですが、時期によって呼び分けていますし、地域によっても違うとも言われています。
ちなみに、小豆は秋に収穫されますが、収穫したての秋には皮が柔らかく粒餡で食べられることが多く、日が経って春になると皮が固くなるため、潰して漉し餡で食べられることが多かったようです。
基本的に同じものなのに、複数の呼び方があるのが紛らわしいので、最近では「おはぎ」で呼び方を統一する傾向がみられます。
「おはぎ」「ぼたもち」を何と呼ぶか?

全体では、83.1%が「おはぎ」と回答しています。
特に20代は94.3%とほとんどの人が「おはぎ」と回答しています。
30~50代も9割弱が「おはぎ」と回答しており、70歳以上の73.0%と比べて「おはぎ」と呼ぶ人が多くなっているようです。
当記事で使用したアンケート
当記事は以下のアンケートを元に作成しました。
出所:食の総合情報サイト ぐるっぱ(https://www.guruppa.jp/)
アンケート名:お彼岸についてのアンケート(2025年3月〆)
調査方法:インターネット調査
調査対象:日本全国 男女
調査期間:2025年2月26日~3月4日
有効回答者数:1,618人

いかがでしたか? アンケート結果を見ると、驚きや新たな発見がありますよね。
ぐるっぱ事務局では、今後も定期的に食や生活にまつわるアンケート結果を掲載していく予定です。
なお、本記事に掲載されているグラフは、「食の総合情報サイト ぐるっぱ」より転載した旨をご記載下されば、有償提供される物への使用を除き、個人・法人問わず無料でご利用頂けます。
最後までご覧下さり有難うございます。次回も宜しくお願いします。

written by