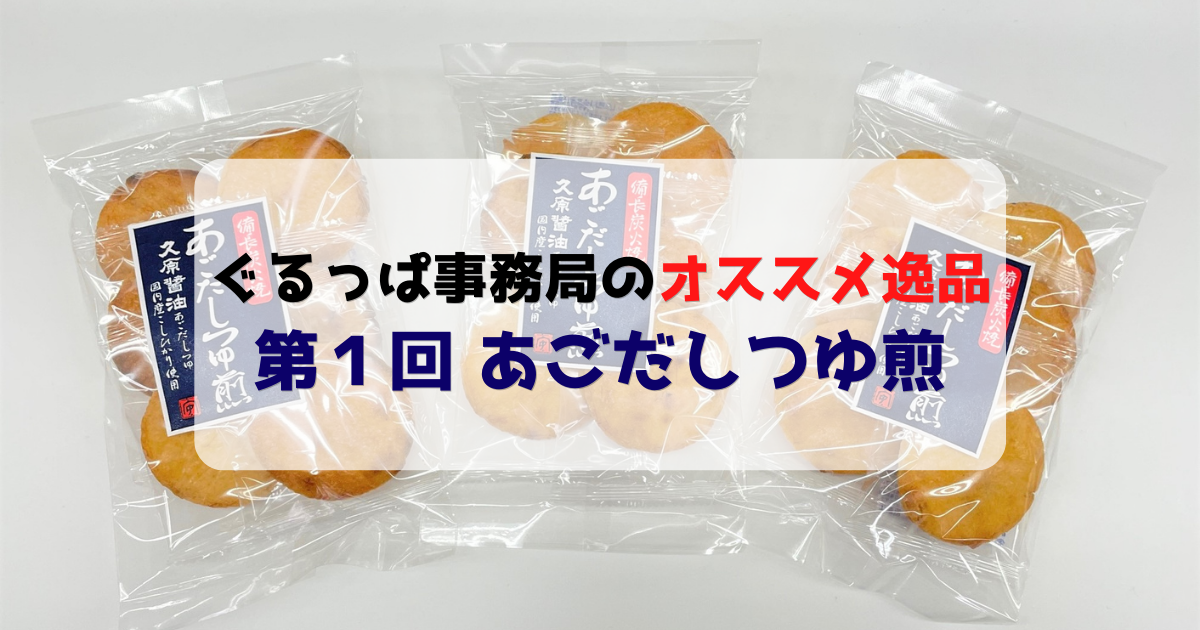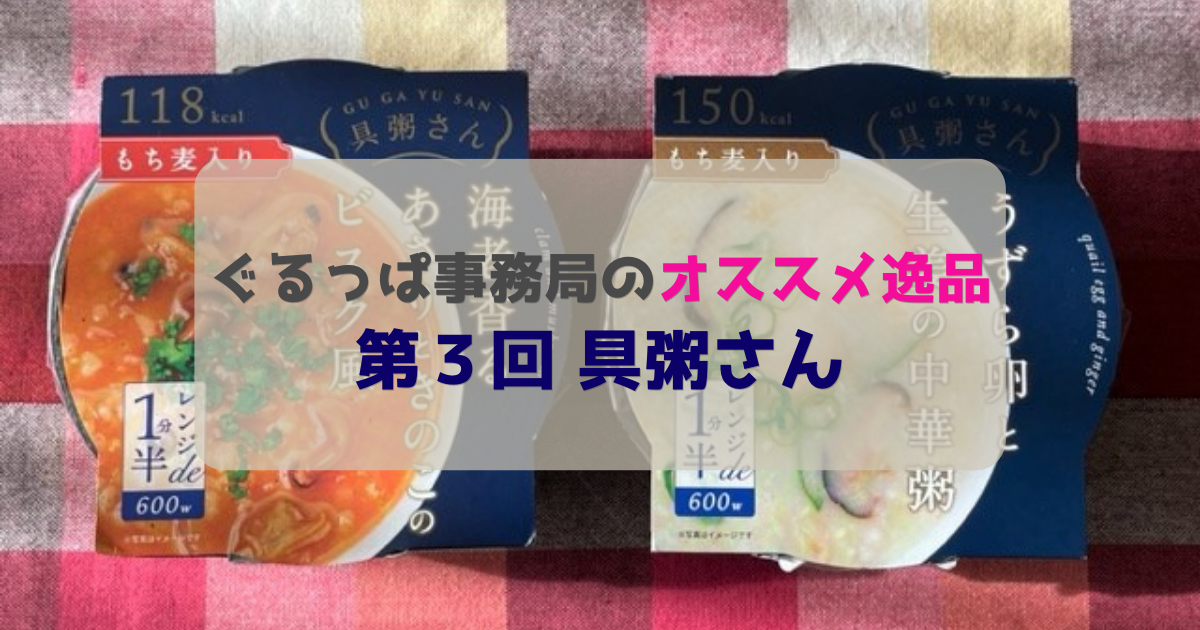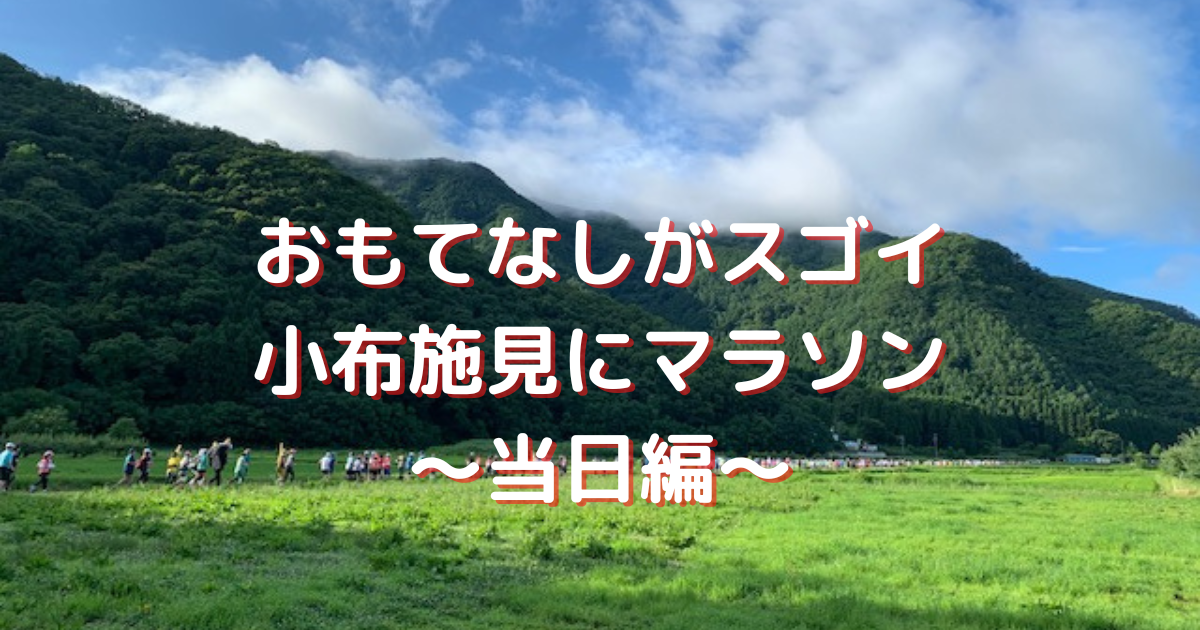

奈良まほろば館に行ってみた
東京にいながら各県の名産品が楽しめる、自治体アンテナショップをご紹介!今回は東京・新橋にある奈良県のアンテナショップ「奈良まほろば館」をご紹介いたします。
美しき古都・奈良の魅力が凝縮「奈良まほろば館」
奈良県は、東大寺の大仏様や鹿が戯れる奈良公園の風景であまりにも有名ですが、実はそれだけではない、奥深い魅力に満ちた場所です。
いにしえの時代より積み重ねた文化と美しい自然がもたらす、観光・食・農産物・伝統工芸。 日本のはじまりの地、奈良にはここにしかない豊かさがあります。本記事では、悠久の歴史と豊かな自然が育んだ奈良と、奈良まほろば館の魅力をたっぷりとお届けします。
●●●住所・営業時間・URLなど●●●
<住所>
〒105-0004 東京都港区新橋1丁目8−4 SMBC新橋ビル 2階 1F・2F
<TEL/営業時間>
1階ショップ
TEL: 03-6263-9656 / FAX: 03-6263-9657
営業時間:11:00~20:00
定休日:年末年始
1階Cafe & Bar まほら
TEL: 03-6263-9656 / FAX: 03-6263-9657
営業時間:11:00~19:30(L.O.19:00)
定休日:年末年始
2階TOKi (Restaurant & Bar)
TEL: 03-6228-5665 / FAX: 03-6228-5661
営業時間:Restaurant 火曜~土曜12:00〜15:30 (L.O. 13:30) 18:00〜22:00 (L.O. 19:30)
Bar 火曜~土曜 12:00〜15:00 (L.O. 13:30) 17:30〜22:30 (L.O. 21:00)
定休日:月曜日、日曜日、お盆、年末年始
<ホームページ>
https://nara-mahoroba.pref.nara.jp/
<Facebook>
https://www.facebook.com/naramahorobakan
<Instagram>
https://www.instagram.com/p/DOUSmrWgXW4/
<奈良まほろば館オンラインショップ>
https://store.mahorobashop.jp/
<アクセス>
JR新橋駅 銀座口より徒歩約3分
東京メトロ銀座線 新橋駅1番出口より徒歩約3分
東京メトロ銀座線 銀座駅A1出口より徒歩約8分
<地図>
●●●フロア案内●●●
1階ショップ
(筆者撮影)
(筆者撮影)
銘菓や伝統工芸品など、奈良で生まれた魅力的な商品それぞれがもつストーリーを丁寧にご紹介します。日々の生活に取り入れることで暮らしが豊かになるような奈良の逸品を取り揃えています。
おすすめ商品は林とうふ店の「田舎あげ」。外はカリッと中はふわっとした厚揚げは奈良まほろば館の人気ナンバーワン商品なんだとか。両面を軽く焼いて食べてみてください!
(筆者撮影)
1階Cafe & Bar まほら

(画像提供:奈良まほろば館)
奈良県産のミルクやフルーツを使用し、季節に合わせたかき氷を一年中お楽しみいただけるほか、奈良の歴史と深い関わりを持つ日本酒や、新しい奈良を感じるこだわりのクラフトビール、気軽に奈良を味わえるフードメニューも揃っています。
1階観光案内
(画像提供:奈良まほろば館)
奈良観光のお手伝い。奈良を知り尽くした観光コンシェルジュが旬の奈良情報をご案内いたします。
2階TOKi (Restaurant & Bar)

(画像提供:奈良まほろば館)
(画像提供:奈良まほろば館)

(画像提供:奈良まほろば館)

(画像提供:奈良まほろば館)
奈良の生産者と連携して、季節の素材や奈良の風土と歴史を感じていただけるよう料理を構成しており、レストランでは季節に合わせ少しずつ移ろうコース料理を、バルエリアではカジュアルな単品をアラカルトで、奈良の地酒やスペインワインとともにお楽しみ頂けます。そしてなんと令和7年9月25日に発表された「ミシュランガイド東京2026」に一つ星として掲載されています。東京都内の自治体アンテナショップ併設のレストランがミシュランに掲載されているのは奈良県が唯一!なんと2023年以降4年連続の掲載となりました。ご予約方法等については是非ホームページをご覧ください!
2階イベントルーム
奈良まほろば館では毎月様々な展示や講演が行われています。体験イベントや講演への参加申し込みはホームページ内「Event」の各講座ページから。
25年9月講演例:「歴史講座・人物編豊臣秀長~大河ドラマが10倍楽しくなる~」「『万葉集』を楽しもう~古代史とともに」等。
奈良の歴史や文化に触れ、体感する機会が沢山準備されていますので是非ホームページをご覧ください。
奈良の農産物~大和の伝統と革新~

イメージ画像(引用元:PhotoAC)
奈良はその長い歴史と共に豊かな食文化を育んできました。「大和野菜」もその一つ。
20種類以上の伝統野菜が大和野菜として登録され、奈良伝統の特産品としてブランド化しており、その特徴をアピールしています。「大和まな」はその代表ともいえ、葉物野菜の一種で、漬物や煮物に適しており、冬の寒さや霜にあたると甘さが格段に増すのが特徴です。奈良時代に書かれた「古事記」にも「菘」としてその原種が登場するほど歴史の長い大和まなですが、以前は収穫後に葉が黄色くなりやすく、流通に課題がありましたが平成18年から品種改良が進み収穫後の黄変が改善。伝統野菜に技術革新が加わり生産・消費拡大が進んでいます。
奈良まほろば館でも大和野菜の取り扱いがありますので足を運んでみてください。
(筆者撮影)

イメージ画像(引用元:PhotoAC)
また、奈良県は柿の一大産地としても知られています。特に五條吉野地域を中心に生産されており、「富有柿」や「刀根早生柿」といったブランド柿の生産で知られています。奈良の柿の歴史は古く、奈良時代に書かれた「正倉院文書」にも記録が残っています。そんな奈良の柿は今ではハウス栽培が盛んにおこなわれており、7月から収穫・出荷が始まります。ハウス栽培を行うことで収穫を早めるだけでなく、雨や災害の影響を受けにくいため、肥培管理や水分管理を行いやすく、糖度が平均で16度、時には18度にもなる甘い柿となります。
このように奈良の農産物は長い歴史の中で育まれてきた伝統に革新を加え、現代に繋げています。
奈良まほろば館ではとオンラインショップでは柿を使った商品を沢山取り扱っています。
その中でも筆者のおすすめは「柿もなか」。白あんを使わず柿を炊き込んで作った餡に吉野産の新鮮な柚子がアクセント。豊かな柿の甘みと柚子のさわやかな香りが絶品。是非ご賞味ください!
(筆者撮影)
古都の食文化が育んだ郷土料理の豊かな味わい
奈良は、日本の歴史の中心地として栄えながら、遣唐使などにより大陸の文化がもたらされ、独自の文化を育んできました。食文化もまた、古都ならではの歴史的背景に加え、盆地という地理的特性が育んだ、豊かな山の幸・川の幸、そして古来からの知恵と工夫が凝らされた郷土料理として長い年月をかけて独自の文化となりました。ここではその郷土料理をいくつかご紹介いたします。

イメージ画像(引用元:PhotoAC)
奈良の郷土料理として最も有名なものの一つが「柿の葉ずし」です。吉野地方が発祥とされ、古くから保存食として親しまれてきました。柿の葉には、殺菌・防腐効果のある成分が含まれており、これによって魚やご飯を新鮮な状態で保つことができます。鯖や鮭、鯛などの切り身を乗せた一口サイズの酢飯を、一枚一枚丁寧に柿の葉で包むことで、柿の葉の清々しい香りが酢飯と魚に移り、上品で奥深い味わいを生み出します。一口食べると、柿の葉の香りが口いっぱいに広がり、どこか懐かしい気持ちにもなります。奈良発祥の郷土料理ですがお箸を使わずに食べられるその簡便性から駅弁としても人気で全国的な知名度を誇ります。
奈良まほろば館1階Cafe & Bar まほらでは軽く炙った柿の葉ずしを楽しむことができます。そのままでももちろんおいしく食べることができる柿の葉ずしですが少し炙ることで鯖や鮭の香ばしい味わいを楽しむことができますので是非一度ご賞味ください。

イメージ画像(引用元:PhotoAC)
奈良県桜井市三輪地方は、そうめん発祥の地として知られています。その歴史は古く、1200年以上の歴史を持つと言われています。冬の厳しい寒風が水分を自然に素早く飛ばすことで作られる三輪そうめんは、細く、コシが強く、滑らかな舌触りが特徴です。茹でた際に麺が伸びにくく、つるりとした食感は、暑い夏にはもちろん、寒い時期にはあたたかい「にゅうめん」として一年を通して楽しめます。油を塗って、細く伸ばす技術は鎌倉時代に中国から伝わり、室町時代にはほぼ製法が完成。奈良の豊富な水が小麦を育み、水車製粉が発達したことにより、良質な小麦粉が製造され、三輪そうめんは職人の手によって一本一本丁寧に作られてきました。江戸時代のグルメ本である「日本山海名物図会」には、三輪そうめんが日本一との記載もあり、古くからその品質は認められてきました。今でも機械化が進む中、すべての工程に人の手が入るのも三輪そうめんの特徴の一つです。
奈良まほろば館では1階のショップで三輪そうめんが購入できるほか、1階Cafe & Bar まほらでは夏は冷やして、冬はにゅうめんにて三輪そうめんを楽しむことができます。また柿の葉ずしとのセットメニューもありますのでこちらも是非ご賞味ください。また、オンラインショップでも三輪そうめんのお取扱いがありますのでこちらもあわせてチェックしてみてくださいね。
幻の逸品も!奈良おすすめグルメ

(引用元:農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」)
奈良県宇陀市ある菓子店松月堂で作られる「きみごろも」。見た目はまるで厚揚げのようでありながら、その食感と上品な甘さが多くの人々を魅了しています。きみごろも最大の特徴は、その儚い口溶けです。卵白をしっかりと泡立ててメレンゲにし、砂糖や寒天、はちみつを加えて固めます。このメレンゲの泡立てには、機械ではなく手作業で行う「手だて」が伝統的な製法とされており、これにより、空気を含んだきめ細かく、ふんわりとした食感が生まれます。ただし30分以上かけて泡立てを行うため一日に作ることができる数は限られているそう。また、賞味期限も短く、出会うことができたらラッキー!
奈良まほろば館では毎週金曜日に入荷していますがSNSで度々話題になることもあり人気の商品。筆者が金曜日の夕方に訪れたときにはすでに完売していました・・・。お買い求めの方は早めの来店がおすすめです。
(夏季は入荷を休止していることもありますのでご注意ください。)

イメージ画像(引用元:PhotoAC)
本葛ならではの透明感とぷるんとした食感の吉野本葛の葛餅もおすすめの逸品。秋の七草のひとつとしても知られている葛ですがその歴史は古く、奈良時代の木簡に葛根の記載があるほど。葛根湯に代表されるように昔は薬として使われてきましたが江戸時代になると葛粉を使用したお餅として食べられるようになります。奈良県吉野では良質な水と冬の厳しい寒さという自然条件に恵まれ、そこで作られた吉野本葛が吉野詣での人々に評判となっていきました。
秋から冬にかけて職人が手作業で掘り起こした葛の根を粉砕し、水の中で何度も揉み込むことでデンプンを水に溶かし出します。このデンプンを溶かした液体を一晩置き、沈殿したデンプン(粗葛)から上澄みのアクや不純物を捨てます。極寒の冷たい水を使い、撹拌と沈殿、水の入れ替えを繰り返し、デンプンを研ぎ澄ましていきます。この作業は「吉野ざらし」と呼ばれる伝統的な製法で、冷水を使うことで、雑菌などの不純物の発生を防ぎ、純白で良質なデンプンを得ることができます。この気の遠くなるような精製作業を繰り返すことで、最終的に葛根から採れる純度の高い吉野本葛は収穫量のわずか1割程度。この貴重な吉野本葛を使用した葛餅が奈良まほろば館とオンラインショップで購入することができますので是非ご賞味ください。

イメージ画像(引用元:PhotoAC)
梅と言えばお隣の和歌山県のイメージが強いですが、奈良の柿農家の多くが梅もあわせて生産していることから、ハウス柿の生産量日本一の奈良県五條市は梅の産地にもなっています。今回ご紹介するのは奈良県でも生産量が極めて少ない品種「林州」を使用した梅干しです。「林州」は奈良県吉野の在来種で古くから栽培されてきました。しかし果皮が収穫期に雨にあたるだけでやぶれるほど薄く、果肉が柔らかいため青果での流通が難しく、比較的取扱いやすい品種への植え替えが進んだこともあり、生産量が減少しており、県外ではめったに出会うことができないまさに幻の逸品。そんな貴重な「林州」と食塩、しそだけでつくられているのが林州むかし梅干しです。一つ一つ丁寧に収穫された貴重な梅を使用し昔ながらの製法で作られたこの梅干しはさわやかなしその香りとしょっぱさが食欲をそそります。は奈良まほろば館とオンラインショップで購入できますのでご飯のおともにいかがでしょうか。
(筆者撮影)
(筆者撮影)
奈良県にはその長い歴史を感じさせる伝統料理だけでなく、貴重な逸品が沢山あります。ここでは紹介しきれないおすすめ品もありますので奈良まほろば館とオンラインショップをのぞいてお気に入りを探してみてください。
奈良まほろば館で伝統工芸にふれる
奈良は、日本の歴史の中心地として栄え、仏教文化や宮廷文化が花開いた地です。そのため、古くから都の需要に応える形で、様々な工芸品が生まれ、現在までその技術が受け継がれています。アンテナショップといえばその地方の食べ物を購入できるイメージが強いですが、奈良まほろば館では伝統工芸品も多く扱っており、その文化と技術にも触れることができます。ここではその一部をご紹介いたします。

イメージ画像(引用元:PhotoAC)
赤膚焼は、奈良市赤膚山付近で産する陶器です。豊臣秀吉の弟、豊臣秀長が大和郡山城を築城した際に、常滑から陶工を招いて赤膚山で窯を開き、茶器を作らせたのが始まりと言われています。特徴は、乳白色の柔らかい肌合いと、桃山時代に生まれたと言われる「奈良絵」と呼ばれる素朴で可愛らしい絵付けです。茶器、花瓶、湯呑みなど、様々な作品が作られており、その清楚で気品のある風合いは、多くの人々に愛されています。
奈良まほろば館では1階のショップで赤膚焼の取り扱いがあるほか、2階TOKi (Restaurant & Bar)では赤膚焼の器も使われており、お料理を引き立てています。
(筆者撮影)
奈良団扇は、その繊細な美しさと実用性を兼ね備えた、奈良を代表する伝統工芸品です。奈良団扇の起源は、春日大社に伝えられた「団扇」にあるとされ、その神官の手内職として作られたのが始まりと言われています。奈良団扇の最大の特徴は、和紙に施された華麗な透かし彫りと、非常に細く数の多い竹骨にあります。団扇の命ともいえる竹骨は、一般的な団扇の倍以上にあたる60本から90本もの数が用いられることが多く、プラスチックの団扇の骨組みの約三分の一ほどに細かく割いた竹を丁寧に加工していきます。この緻密な骨組みは、非常に高度な技術を要しますが団扇にしなやかさと強さをもたらし、あおぐ際に良質な風を生み出す秘訣となっています。そして、奈良団扇の代名詞とも言える透かし彫りは、「突き彫り」という伝統的な技法によって生まれます。冬の寒い時期に天然の染料で色付けし、裏移りしないよう加工した和紙を団扇10本分の20枚を重ね合わせ、職人が手作りの鋭利な小刀を用い、一気に突き刺すようにして文様を彫り抜いていきます。その後、透かし彫りを施した和紙を竹骨に貼り合わせる叩き貼りの工程や、竹骨を和紙の上から浮かび上がらせる念付けの作業を経て、涼しげで立体的な美しさを持つ奈良団扇が完成します。こうした作業はすべて手作業で行っていますが、現在ではその技術を持つ奈良団扇の製造販売は県内の一軒のみとなっており、機能美と装飾美を兼ね備えた奈良団扇は貴重な品となっています。
他にも奈良まほろば館では奈良の伝統工芸品を数多く取り揃えていますので是非足を運んで奈良の文化・伝統にふれてみてください。
大河ドラマ「豊臣兄弟!」ゆかりの地を巡る
2026年1月~放送のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』は、兄豊臣秀吉の天下取りを支えた弟・秀長(ひでなが)の目線で戦国時代を描く作品。そんな秀長が晩年を過ごしたのが、大和国(現在の奈良県)です。秀長ゆかりの地、奈良県大和郡山市・宇陀市・高取町の観光スポットをご紹介します。

(画像提供:奈良まほろば館)
郡山城は、地元の戦国大名筒井順慶の築城に始まり、豊臣秀長が100万石の居城として大改修を行った城で、彼が亡くなるまで過ごした場所です。現在は石垣や堀が残る城跡として整備されており、桜の名所としても知られています。約800本のソメイヨシノ等の桜が植えられており、「日本さくら名所100選」にも選ばれています。天守台に登ると、秀長も眺めたであろう城下町や奈良盆地を一望することができます。

イメージ画像(引用元:PhotoAC)
また郡山城から歩いて15分程のところにあるのが「大納言塚」です。
天正19年(1591年)に没した秀長の墓所で大和郡山市の指定文化財です。豊臣家の滅亡後、菩提寺が京都に移されたこともあり、一時荒廃しましたが安永6年(1777年)に整備され塀や五輪塔が建てられています。

イメージ画像(引用元:PhotoAC)
中世に秋山氏の本城として築城された宇陀松山城。その後秀長が大和郡山に入部したことをきっかけに豊臣配下の大名が城主となり、城は大規模な改修を経て郡山城・高取城と合わせた三城体制で大和国支配の重要な拠点とされました。
大坂夏の陣を経て城は破却され現在では石垣の一部が残るのみとなっていますが高台に位置する山城として東国へ睨みをきかせていた宇陀松山城。城下町は今もその当時の雰囲気を残した歴史ある街並みが残っていますのであわせてお楽しみください。

イメージ画像(引用元:PhotoAC)
高取町高取山に築かれた高取城は日本三大山城の一つ。以前は秀長の家臣、本多利久によって整備・拡充され堅固な石垣を持つ難攻不落の城となりました。明治に入り、廃城となりましたが現在も石垣は当時の姿を残しており、その壮大な規模を楽しむことができます。
高取城の比高(麓から本丸までの高さ)は390mと山城で最大の高さを誇ります。城下町(土佐街道)より望むその姿は「巽高取 雪かと見れば 雪でござらぬ 土佐の城」と詠われており、今ではなくなってしまったその城郭は白く、姫路城のような城郭であったと想像できます。※「土佐」は高取の旧名
秀長ゆかりの地と当時の豊臣体制の重要拠点となった三城。大河ドラマの放送にあわせて注目が高まりますので是非訪れてみてください。
飛鳥・藤原を世界遺産に
2025年1月、政府は天武天皇などの宮殿があったとされる明日香村の飛鳥宮跡や、極彩色の壁画が見つかった高松塚古墳、橿原市の藤原宮跡など19の文化財を構成資産とする「飛鳥・藤原の宮都」をユネスコに推薦しており、世界遺産登録への期待が高まっています。
飛鳥と藤原は、日本の古代国家形成期に日本の首都が置かれた場所です。この地域には、天皇の宮殿や寺院、陵墓(天皇や皇族の墓)などが集中しており、日本の政治・文化の中心地として機能していました。

イメージ画像(引用元:PhotoAC)
592年の推古天皇の即位から平城京に遷都する約120年間を飛鳥時代と呼び、遣隋使の派遣による東アジアとの交流と政治改革と政変を繰り返し日本の礎を作り上げた時代です。
飛鳥時代は長く続いた古墳文化の終末にあたる時代となり、権力の象徴として作られてきた巨大な前方後円墳は方墳や八角墳へとその姿を変え、高松塚古墳やキトラ古墳には大陸的な壁画が描かれ、東アジアとの政治的・文化的な交流を通して思想や芸術が伝わっていたことを示しています。

イメージ画像(引用元:PhotoAC)
また、この時代には日本初の本格的な寺院法興寺(飛鳥寺)が建立され仏教が広まり始めます。現在の本堂は鎌倉時代に一度焼失し、江戸時代に再建されていますが、御本尊の銅造釈迦如来坐像(飛鳥大仏)は日本最古の仏像であり、重要文化財に指定されています。

イメージ画像(引用元:PhotoAC)
藤原宮跡は持統・文武・元明の三代の天皇が治めた藤原京の中心地にあり、内裏・大極殿・朝堂院が並び、飛鳥宮から進められてきた中央集権の確立がうかがえます。藤原京が都とされた期間は約16年間と長くはありませんが、その大きさは平城京・平安京を上回るとされており、国の仕組みの確立と繁栄が示されています。万葉集にも数多く詠われてきた大和三山に囲まれたその地は現在では当時の姿を再現した朱塗りの列柱が数か所設置されているのみとなっていますが、菜の花や蓮、コスモスなど季節の花々が植えられ、当時の都を彩っています。
「飛鳥・藤原の宮都」が世界遺産に登録されれば、日本の古代国家形成の過程と、その文化を世界に発信する貴重な機会となります。この地域に残る数々の遺跡や史跡は、日本の歴史の礎を築いた人々の息吹を今に伝えています。ぜひ一度、飛鳥・藤原を訪れ、その歴史的な価値と豊かな自然を感じてみてください。
他にも魅力的な観光スポットが沢山ありますので奈良まほろば館1階観光案内コーナーの観光コンシェルジュへ旅行の相談をしてみてはいかがでしょうか。観光案内のチラシも沢山ありますので奈良への旅行を計画する際はぜひ奈良まほろば館までお越しください。
さいごに
いかがでしたでしょうか。東京にいながら、悠久の歴史と豊かな自然が息づく、美しき古都・奈良を体感することができる「奈良まほろば館」。おいしいグルメはもちろん、奈良の伝統と文化にもふれることができますので是非一度お店に足を運んでみてください。
今回はここまでとなります。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
よろしければ下のオレンジのリンクから他のアンテナショップの紹介記事もご覧ください。

written by